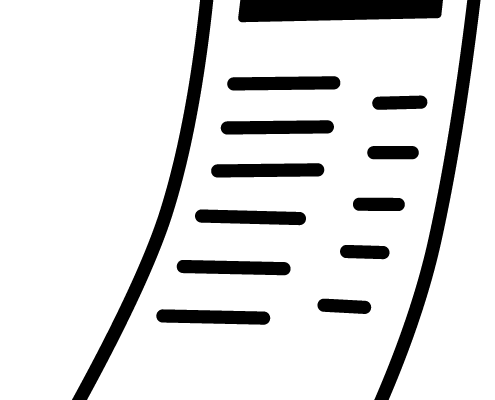
いまさら聞けない「価格の決め方」にはどんな方法がある?――これだけ知れば、自信を持って設定できる
商品やサービスを提供する際、「いくらで売るか」は売上に直結する重要な意思決定です。特に起業や小規模事業者にとっては、一歩間違えると利益が取れず、場合によっては赤字になってしまうことも。本記事では代表的な価格づけの方法を、生活や実務に即してシンプルに整理しました。
① 原価+利益方式(コストプラス価格)
これは、必要なコストに一定の利益を乗せて価格を決める方式です。
○ 利点
- シンプルでミスが少ない
- 最低ラインが明確
× 注意点
- 競合の価格や顧客の「価値」を反映しにくい
- 価格が高すぎたり安すぎたりする可能性
② 競合に合わせる方式(市場価格ベース)
他社が販売している価格に合わせる方法です。
○ 利点
- 顧客目線で比較しやすい
- 競争力を保ちやすい
× 注意点
- 利益が出ない可能性がある
- 価格競争に巻き込まれるリスク
③ 顧客が感じる価値で決める方式(価値ベース価格)
「お客様がどれだけ価値を感じるか」によって価格を設定する方法です。
○ 利点
- 高利益が狙いやすい
- ブランディングに有効
× 注意点
- 価値の裏付け調査が必要
- リサーチコストがかかる
④ 新製品・新展開向きの価格戦略
・価格スキミング
最初に高価格で販売し、徐々に価格を下げていく方式
・市場浸透価格
導入時に安価で販売し、後から価格を上げていく方式
⑤ 固定的・変動的に価格を変える方式
・ダイナミックプライシング
需要や時間に応じて価格を変える方式(例:Uber、航空券)
・地域別価格設定
地域によって価格を調整する方式(例:送料の違い)
⑥ その他の工夫型価格(心理・複数設定)
・心理価格
98円・499円など端数価格を用いて安さを印象づける
・バンドル価格
セット販売でお得感を演出し、客単価を上げる
⑦ どの方法を選ぶべきか?
- 目指すイメージ
- コストと利益の構造
- 競合状況
- 顧客が感じる価値
- 価格弾力性
- 組み合わせ戦略
まとめ:価格設定は「戦略」として計画的に
価格設定は単なる計算作業ではなく、戦略的な意思決定です。市場の声、自社の強み、顧客のニーズを総合的に捉え、納得感と利益を両立できる価格設計を目指しましょう。
【無料相談のご案内】
弊社では、中野裕哲を中心とした所属専門家チーム(起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、中小企業診断士、FP、元日本政策金融公庫支店長、元経済産業省系補助金審査員など)が一丸となって、幅広い起業支援・経営支援を行っております。
起業の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。無料相談も行っているので、ぜひ一度、ご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル
お問い合わせフォーム
この記事を書いた人
中野裕哲/Nakano Hiroaki
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP技能士。大正大学招聘教授(起業論、ゼミ等)
V-Spiritsグループ創業者。税理士法人V-Spiritsグループ代表。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「ベストセラー起業本」の著者。著書20冊、累計25万部超。経済産業省後援「DREAMGATE」で12年連続相談件数日本一。
【まるごと起業支援(R)・経営支援】
起業コンサル(事業計画+融資+補助金+会社設立支援)+起業後の総合サポート(経理 税務 事業計画書 融資 補助金 助成金 人事 給与計算 社会保険 法務 許認可 公庫連携 認定支援機関)など
【略歴】
経営者である父の元に生まれ、幼き頃より経営者になることを目標として過ごす。バブル崩壊の影響を受け経営が悪化。一家離散に近い貧困状況を経験し、「経営者の支援」をライフワークとしたいと決意。それに役立ちそうな各種資格を学生時代を中心に取得。同じく経営者であるメンターの伯父より、単に書類や手続を追求する専門家としてではなく、視野を広げ「ビジネス」の現場での経験を元に経営者の「経営そのもの」を支援できるような専門家を目指すようアドバイスを受け、社会人生活をスタート。大手、中小、ベンチャー企業、会計事務所等で営業、経理、財務、人事、総務、管理職、経営陣等、ビジネスの「現場」での充実した修行の日々を送ったあと、2007年に独立。ほかにはない支援スタイルが起業家・経営者に受け入れられ、経済産業省「DREAM GATE」にて、面談相談12年連続日本一。補助金・助成金支援実績600件超。ベストセラー含む起業・経営本20冊を出版。累計25万部超。無料相談件数は全国から累計3000件を超す。

この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。





























