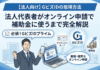損益計算書で資金繰りを考えるのは注意が必要!?
おはようございます。11/30日、「本みりんの日」です。全国味淋協会が制定。「い(1)い(1)み(3)りん(0=輪)」の語呂合せと、鍋物などで本みりんを使う季節であることから。
損益計算書と資金繰りの誤解
今回は、【損益計算書で資金繰りを考えるのは注意が必要!?】です。私は、銀行員時代に営業担当として法人の決算書をたくさん見てきました。1年目、2年目の頃は決算書を見るのはとても新鮮でたくさんの間違った思い込みをしていました。それは、売上がたくさん上がっていて利益がでている会社はお金に困らず潤沢に預金があるんだろうと。今思い返すと大変恥ずかしい話ですが、そうでした。しかし、それに似た言葉をよく耳にします。〇〇さんは大きく商売しているから・・・。〇〇さんは儲かって仕方がなくて・・・。案外こんな思い込みをしている人は多いのではないかと思っています。規模や利益が大きく出れば、それに伴い消費税や法人税等も大きくなります。対外的な数字はよくとも、実はお金回りは苦戦しているといった企業はたくさんあります。
なぜ注意が必要なのか
では、なぜ損益計算書で資金繰りを考えるのは注意が必要かを解説していきます。損益計算書に記されている順番は、上から売上高から売上原価を差し引き、販管費を差し引きという足し算と引き算の順番のことです。もちろん、損益計画を立てる最終目標は損益計算書で利益を出すことです。しかし、資金繰りの計画は損益計画のとおりにいくわけではありません。損益計算書の性質上、売上高を一番上に持ってきているだけで、必ずしも売上高として最初に入金されるとは限らないのです。
損益計算書と資金の流れの違い
まずは、損益計算書の順番通りにお金が出入りするわけでないということを、しっかり理解することが大事です。業種業態によって様々ですが、大半の会社では商品を販売する為に・①仕入れ、商品PRの為に・②宣伝広告や人件費をかけて商品を・③販売します。この流れだけを見ても、損益計算書とは順番が異なります。この場合はお金が先に出ていき後からお金が入ります。きちんと、自社の業種業態に合わせた、お金の出入りの順番を知っておくべき必要がありますね。
【無料相談のご案内】
起業の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひ一度、ご相談ください。お問い合わせお待ちしております!

この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。