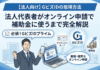金融機関との契約書(最終回)|「抵当権設定契約書」とは?内容と注意点をわかりやすく解説
これまで金融機関と締結する契約書について解説してまいりましたが、今回が最後となります。
「抵当権設定契約書」とは?
今回は「抵当権設定契約書」と言われる契約書です。
創業融資などで無担保での融資を受けている場合、基本的には締結しない書類となります。
文字通りですが、金融機関が「抵当権」を担保物件に「設定」するための契約書であり、つまりは不動産担保を取りますよ、という契約になります。
抵当権を設定するとはどういうことか?
担保に取るというのは、具体的には不動産登記(法務局)の乙区といわれる欄に、
- 設定日
- 債務者
- 債権者
- 債権額(極度額)
を登記し、その不動産が●●銀行の担保に入っているということを、第三者に知らしめる手続きを踏みます。
この一連の流れを「抵当権を設定する」といい、その根拠となる契約書が「抵当権設定契約書」なのです。
どのような場合に「抵当権設定契約書」を締結するのか
工場や倉庫、店舗などを購入する資金を借りる場合には、基本的に購入する不動産に抵当権を設定します。
事業用の資金とは一線を画した、「住宅ローン」や「アパートローン」でも実は抵当権設定契約書を締結しています。
抵当権設定契約書の内容
役割はシンプルですが、内容はどのようになっているのでしょうか。以下に主要な項目を解説します。
(契約日)
抵当権を設定する日となります。多くの場合、金融機関から融資を受ける日と同じです。
(債権者)
金融機関や保証会社などです。
(債務者)
融資を受けた人です。
(抵当権設定者)
その不動産の所有者です。多くの場合、債務者と同じです。
(債権額)
融資を受けた金額です。
場合によっては根抵当権という設定形態になり、融資を受けた金額とは違う設定額(この場合は極度額と言います)を設定するケースもあります。
(融資の内容)
抵当権設定契約書の書面に、融資の詳細を記入します。
借入金額・借入日・弁済日・利息・遅延損害金などです。
実際にはこの情報の一部が不動産登記に登記されます。
(対象物件)
抵当権を設定する(=担保に入れる)物件を明示します。
登記上の住所(地番・家屋番号など)、地目(種類)、構造、面積などです。
登記上の住所は、郵便が届く一般的な住所(住居表示と言います)とは違うことも多いので注意しましょう。
創業期の経営者が知っておくべきポイント
創業融資ではほとんどお目にかかることはありませんが、事業を進めていくにつれ設備投資で融資を受けることもあるかと思います。
将来のためにも、内容については知っておいた方が良いでしょう。
まとめ:金融機関との契約書シリーズを終えて
以上で、金融機関と締結する契約書についての解説は終了です。
経営をしていく上では多くの契約書を交わすかと思いますが、金融機関と締結する契約書は経験不足のまま締結に至ることも多く、事前に予備知識があるとないとでは大きな違いがあります。
契約書だけでなく、金融機関取引にご不安があればお気軽にお声がけください。
【無料相談のご案内】
起業の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひ一度、ご相談ください。お問い合わせお待ちしております!

この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。