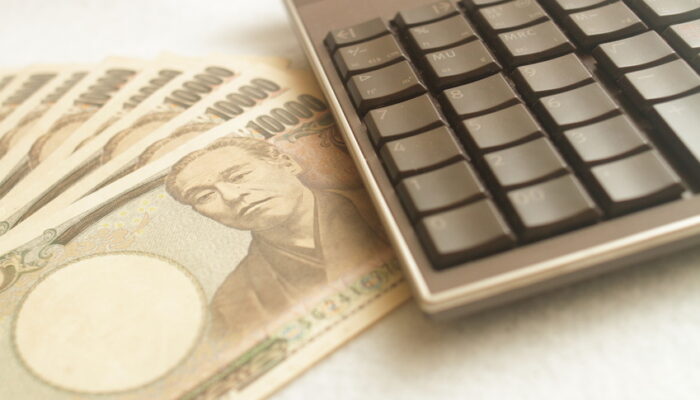
ビジネスモデルの「どのように提供するか」を解剖!価格設定の5つの視点も解説
こんにちは!いつもありがとうございます。
V-Spiritsグループ代表で、
爆アゲ税理士 中野です。
今回は、ビジネスモデル構築シリーズの中でも、
特にご質問が多いテーマ、
「どのように提供するか」についてお話しします。
実はここ、
ビジネスモデルの中で一番差がつきやすく、
かつ一番考える範囲が広いパートです。
目次
- ビジネスモデル3要素のおさらい
- 「どのように提供するか」が重要な理由
- なぜ「3」はこんなに広範囲なのか
- 5W1Hと「どのように提供するか」の関係
- まずは価格の決め方から考えよう
- 価格設定で検討すべき5つの基本要素
- 価格は戦略そのもの
- まとめ
- よくある質問(FAQ)
ビジネスモデル3要素のおさらい
まずは基本から確認しましょう。
ビジネスモデルは、次の3つの要素で構成されています。
- 誰に
- 何を
- どのように
この3つは、
どれか1つが欠けても成り立ちません。
特に起業初期の方は、
「2 何を(商品・サービス)」に意識が集中しがちですが、
実際には「3 どのように」で失敗するケースが非常に多いのです。
「どのように提供するか」が重要な理由
同じ商品・同じサービスでも、
「どのように提供するか」が違うだけで、
売上も利益も、まったく別物になります。
たとえば、
- 営業時間が違う
- 提供スピードが違う
- 価格帯が違う
- 売り方(対面・Web)が違う
これだけで、
お客様の感じる価値は大きく変わります。
つまり、
「どのように提供するか」=競争力そのものなのです。
なぜ「3」はこんなに広範囲なのか
「どのように提供するか」は、
非常に守備範囲が広い要素です。
なぜなら、
ビジネスの運営・設計・仕組みのほぼすべてが、
ここに含まれるからです。
そこで理解しやすいのが、
次に紹介する5W1Hとの関係です。
5W1Hと「どのように提供するか」の関係
5W1Hで整理すると、
「2 何を(What)」以外は、
すべて「どのように提供するか」に関係します。
- When(いつ)
営業時間、定休日、提供タイミング、曜日、時間帯など - Where(どこで)
リアルかWebか、立地、商圏、サイト、導線など - Who(だれが)
誰が対応するか、担当者、採用する人材の質 - Why(なぜ)
なぜその事業をやるのか、背景、想い、ストーリー - How(どのように)
価格、集客方法、マーケティング、配送、提供方法など
見ていただくと分かる通り、
ほぼ全部ですよね。
だからこそ、
「どのように提供するか」は、
ビジネスモデルの中でも特に奥が深いのです。
まずは価格の決め方から考えよう
本来であれば、
この「どのように提供するか」について、
すべてお話ししたいところですが、
まず最初に取り上げたいのが、
「価格の決め方」です。
なぜなら、価格は、
- 利益を左右する
- 客層を決める
- ブランドイメージを作る
という、
非常に影響力の大きな要素だからです。
価格設定で検討すべき5つの基本要素
モノやサービスの価格を決めるときには、
次の5つの要素を検討するのが基本中の基本です。
① 自社コスト(原価構造)
原材料費、人件費、家賃、外注費など。
まずは現実的に利益が出る価格を把握します。
② 顧客受容性(値頃感)
ターゲット顧客が、
「その価格なら払える」「妥当だ」と感じるかどうか。
③ 競合戦略(競合との比較)
競合より高いのか、安いのか。
なぜその価格なのか、説明できる必要があります。
④ ブランディング(高い・安いのイメージ)
価格は、そのままブランドメッセージです。
安売りか、高付加価値か、立ち位置を明確にします。
⑤ 提供価値との適合
「満足度」と「価格」のバランスです。
高いなら高い理由があるか。
安いなら安い理由があるか。
この5つは、
どれか1つでも欠けると危険です。
価格は戦略そのもの
価格は、
「とりあえず決めるもの」ではありません。
価格は、
ビジネス戦略そのものです。
価格を決めるということは、
「誰に、どんな価値を、どんな立場で提供するか」
を宣言することでもあります。
ぜひ、
今回ご紹介した5つの視点を、
じっくり考えてみてください。
まとめ
- 「どのように提供するか」は最も広範囲な要素
- 5W1Hのほぼすべてが関係する
- まずは価格設定から考えるのがおすすめ
- 価格設定には5つの基本視点がある
- 価格はビジネス戦略そのもの
次回は、
この価格設定を、
より具体的な事例を使って掘り下げていきます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 価格は後から変更しても大丈夫ですか?
可能ですが、
値上げは特に慎重な設計が必要です。
Q2. 安くしないと売れない気がします
その場合は、
提供価値が正しく伝わっていない可能性があります。
Q3. 原価から積み上げて決めるだけではダメですか?
不十分です。
顧客・競合・ブランド視点を必ず加えましょう。
無料相談もお待ちしております。
中野を指名いただければ、ZOOMなどで直接ご相談にお答えいたします。
【無料相談のご案内】
起業の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひ一度、ご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
この記事を書いた人
中野裕哲/Nakano Hiroaki
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP技能士。大正大学招聘教授(起業論、ゼミ等)
V-Spiritsグループ創業者。税理士法人V-Spiritsグループ代表。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「ベストセラー起業本」の著者。著書20冊、累計25万部超。経済産業省後援「DREAMGATE」で12年連続相談件数日本一。
【まるごと起業支援(R)・経営支援】
起業コンサル(事業計画+融資+補助金+会社設立支援)+起業後の総合サポート(経理 税務 事業計画書 融資 補助金 助成金 人事 給与計算 社会保険 法務 許認可 公庫連携 認定支援機関)など
【略歴】
経営者である父の元に生まれ、幼き頃より経営者になることを目標として過ごす。バブル崩壊の影響を受け経営が悪化。一家離散に近い貧困状況を経験し、「経営者の支援」をライフワークとしたいと決意。それに役立ちそうな各種資格を学生時代を中心に取得。同じく経営者であるメンターの伯父より、単に書類や手続を追求する専門家としてではなく、視野を広げ「ビジネス」の現場での経験を元に経営者の「経営そのもの」を支援できるような専門家を目指すようアドバイスを受け、社会人生活をスタート。大手、中小、ベンチャー企業、会計事務所等で営業、経理、財務、人事、総務、管理職、経営陣等、ビジネスの「現場」での充実した修行の日々を送ったあと、2007年に独立。ほかにはない支援スタイルが起業家・経営者に受け入れられ、経済産業省「DREAM GATE」にて、面談相談12年連続日本一。補助金・助成金支援実績600件超。ベストセラー含む起業・経営本20冊を出版。累計25万部超。無料相談件数は全国から累計3000件を超す。

この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。





























